私が防災士を目指したきっかけは、整理収納アドバイザーとして参加したコンペで「防災」をテーマに発表したことでした。調べていくうちにどんどん興味がわき、自宅が川のそばにあることもあって、もっとちゃんと備えたいと思うように。そんな中で知った「防災士」という資格。最初は「なんだか難しそう」と感じましたが、調べてみると意外と手が届く内容で、思い切ってチャレンジすることにしました。
この記事では、私の体験をもとに、防災士の申し込み方法から教材の内容、自宅学習の進め方までをまとめています。「防災士ってどんなことするの?」「勉強は難しいの?」という方の参考になれば嬉しいです。
防災士とは?
基本概要
防災士とは、一般社団法人日本防災士機構が認定する民間資格で、地域や家庭などで防災・減災に取り組む人材を育成することを目的としています。
対象・難易度・所要期間など
「防災士」と聞くと、消防や救命のプロのような専門職の資格?と思われるかもしれませんが、実は誰でもチャレンジできる資格です。18歳以上であれば特別な資格や経験は不要で、合格率は90%以上。
取得までの流れは、まず教材を使った自宅学習を行い、その後、2日間の講習を受講します。
この講習では、座学に加えて救命救急の実技や確認試験も行われることが多く、別日に試験を受けに行く必要はありません。
申し込みから受講・試験・登録まで、およそ1カ月程度で取得することができます。
実際に学ぶ内容
災害と聞くと、真っ先に「地震」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。けれど実際には、台風・大雨・土砂災害・津波・火山噴火など、日本には多様な災害リスクがあります。防災士の講座や教材では、こうしたさまざまな災害への備えや知識について、体系的に学ぶことができます。
申し込み~教材が届くまで
① HPから申し込む(防災士研修センターが一般的)
もっとも一般的なのは、「防災士研修センター」の公式サイトからの申し込みです。
全国の開催日程を検索でき、Web上で申し込みを完結できます。
▼受講希望日程はこちらから選べます:
https://www.bousaishi.net/application
私が申し込んだのは2025年7月下旬・東京開催分でしたが、土日開催はかなり先まで満席の状態でした。
土日を希望される方は、早めの予約が安心です。
⚠️ 申し込み時の注意
申し込みの際、※救命講習付き(全員必修)と記載が無いコースでは救急救命講習の修了証が別途必要になりますので、ご注意ください。
② 支払い
申し込み後、1週間以内に支払いを済ませることで正式登録となります。
支払い方法は、2025年7月時点では銀行振込と郵便局での支払いのみで、クレジットカード払いはできません。
② 教材一式が届く
研修日の約3〜4週間前に、教材一式が届きます。(※私の場合は5週間前に届きました)
レターパックでポストに投函されるため、日中ご不在でも安心です。

③ 約1ヶ月、自宅学習
教材到着後は、研修日までの約1か月間を使って自宅学習を進めます。まず届いた教材の中身を見て、教本の分厚さに驚きました。
中に入っていたものはこちら:
- 防災士教本(分厚い!)
- 履修確認レポート用テキスト(薄い冊子)+ 解答用紙
- 試験対策ブック(薄い冊子)
- 受講案内や申請書類
費用まとめ(2025年時点)
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 研修講座受講料 | 50,728円 |
| 試験受験料 | 3,000円 |
| 登録料(合格後) | 5,000円 |
| 消費税 | 5,072円 |
| 合計 | 63,800円 |
※自治体によっては補助金制度がある場合もあるので、確認してみて下さい。
※他にも学割があります。
自宅学習って何するの?
教材が届いてから、約1カ月間の自宅学習期間があります。必ずやらければならないのはり履修確認レポートの作成と試験勉強です。私はこんなふうに進めました。
- 履修確認レポートを終わらせる
- 防災士教本を読む(ざっと1周目)
- 履修確認レポートをnotionにまとめる
- YouTubeで耳から学習
- 過去問を解く
- 防災士教本を読む(2周目で理解を深める)
- 試験対策ブックで問題演習
履修確認レポート(講習の初日に提出)
「レポート」と聞いて最初は、自分で文章を書くのかと思っていました。でも実際は、穴埋め式の確認問題でした。
防災士教本を見ながら、該当箇所を探して、同封の解答用紙に書き込んでいく形式です。教本とまったく同じ文章がそのまま載っているので、内容としては難しくありません。
ただし、すべて手書きで記入する必要があります。普段はパソコン作業ばかりの私にとっては、手書きに少し時間がかかり、2日ほどかけてやっと完成しました。
防災士教本を読む(1周目)
1周目はざっと目を通すことを意識しました。どんなことが書かれているのか、まずは全体像をつかむことに専念。とにかく量が多いので、無理せず少しずつ読み進めていきました。
履修確認レポートをNotionにまとめてみた
防災士教本は分厚くて、持ち歩くのも一苦労。そんなある日、ふと思いました。
「履修確認レポートって、大事なところがまとまっているよね。それをパソコンに入力してみようかな。」
私は日頃から愛用しているNotionというアプリを使って、履修確認レポートをそのままPCに入力しました。
実際に入力してみると、読み飛ばしていたところにも目が行き、内容がより頭に入ってきます。さらに、出先でも気軽に見返せるので、とても便利でした。そして何より、防災士に合格した後も、必要な知識をすぐに確認できるようにしたいという思いもありました。
YouTubeで耳から学習
通勤中やスキマ時間には、YouTubeを活用して耳からインプットしていました。
特によく視聴していたのが、防災士試験のポイントを丁寧に解説してくれるこちらのチャンネルです。
優しい口調で聴きやすかったです。しかも1本の動画が短めなので、ちょっとした時間でも無理なく学べます。
さらに、各章の解説のあとに練習問題が出る構成になっていて、インプットとアウトプットの両方ができる点も魅力でした。
過去問に挑戦(Kindle Unlimited)
試験対策として、過去問にも取り組みました。送付された試験対策ブックも、もちろんやるつもりではいました。
でも、実際にどんな問題が出るのか気になって、本番形式の過去問を事前に見ておきたいと思ったんです。そこで活用したのが、AmazonのKindle Unlimited(キンドル アンリミテッド)。月額980円の読み放題サービスですが、初回30日間は無料体験ができます。
実際に問題を解いてみた感想としては、難易度はそこまで高くありません。
教材をしっかり読み、レポートや模擬試験に取り組んでいれば、十分に合格ラインを狙える内容でした。
Excelで“正解チェック表”を作ってみた
過去問は紙とペンで解く方が多いと思いますが、私はExcelが好きなので、ちょっと変わった方法で学習してみました。
過去問の正解を一覧にして、回答を入力すると隣に「正解」か「不正解」が表示されるチェック表を作成。
ゲーム感覚で進められるので、空き時間にパッと取り組むにはちょうどよかったです。毎回間違える問題が分かり、苦手な問題が浮き彫りになるのも良かったポイントでした。
防災士教本を読む(2周目で理解を深める)
試験10日前くらいになって、もう一度、防災士教本を読んでみることにしました。
一通り勉強して過去問も解いていたので、頭には入ってきている感じはありましたが、読み直すことで「あ、ここ見落としてたな」と思うことも。
正直、合格したらもうここまで真剣に読むことって無いと思うので(笑)、最後にもう一度だけじっくり読みました。
試験対策ブックで問題演習
正直に言うと、試験対策ブックの存在を完全に忘れていました・・・気づいたのは試験の直前。焦って、最後の2日間で一気に解きました。
講習会場でも「私も忘れてた!」という声があちこちから聞こえてきたので、意外と見落としている人は多いようです。防災士教本を読むことに夢中になると、つい試験対策ブックの存在を後回しにしてしまいがち。
みなさんは、忘れずに早めに取り組むことをおすすめします。
まとめ
最初は、「防災士なんて自分にできるのかな」「6万円はちょっと高いな」と思い、正直、申し込んだあとも振り込みをギリギリまで躊躇していました。
でも、受講してみて心から「受けてよかった」と思っています。
災害が多い日本で暮らすうえで、防災の知識は誰にとっても必要なもの。防災士の学びは、いざというときに自分や大切な人を守る力になります。
防災バッグや家具の固定など、表面的な備えは目にする機会が増えましたが、「災害とは何か」「どう行動すべきか」を体系的に学べる機会はまだまだ少ないと感じます。
次回の記事では、講習当日の雰囲気や試験の内容、実技の様子などを詳しくご紹介します。
「何を持っていけばいい?」「どんな服装?」「どんな人が来ていた?」など、気になる点をリアルな体験をもとにお届けします。講習をこれから受ける方にとって、不安が少しでも減るような内容になれば嬉しいです。
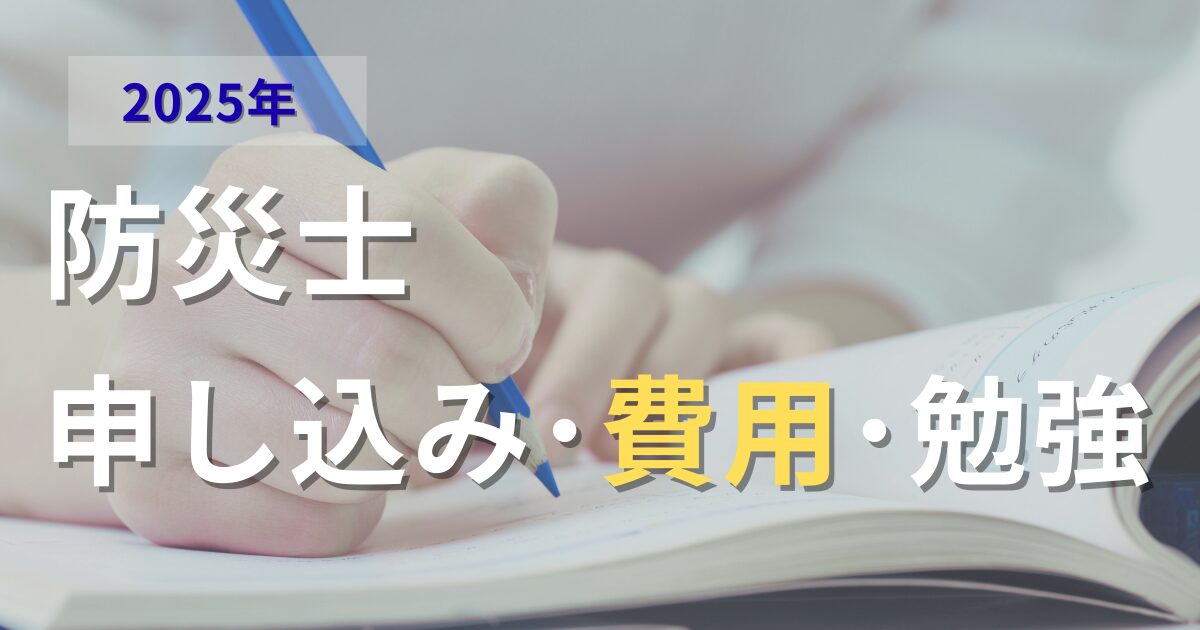




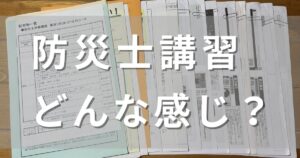
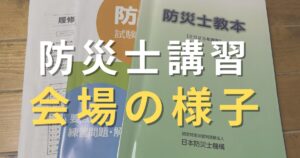

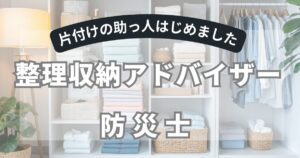
コメント